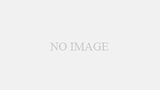「お風呂に入ろう!」と言った瞬間に泣き出したり、逃げ回ったり…。
小さい子どもにとってお風呂は「楽しい場所」にもなれば「苦手な時間」にもなります。
わが家でも最初は苦戦しましたが、いろいろ試すうちに、少しずつお風呂が好きになっていきました。
今日はその体験談と、お風呂を通して得られる教育的メリットについてご紹介します。
体験談① 頭からシャワーで慣れさせる
職場の先輩に「小さいうちから頭からシャワーをかけて慣れさせた方がいい」と言われ、思い切って実践しました。
最初はガーゼで拭いていたのですが、毎日1回は頭からシャワーをかけるようにすると、子どもが自然と自分で目をこすって水気をとるようになりました。
「顔に水がかかる」ことに慣れると、プールや外遊びでも怖がらなくなるのを感じます。
体験談② 親が楽しそうに見本を見せる
子どもに「お風呂は怖くないよ」と伝えるには、親自身が楽しそうに入るのが一番。
私は顔を洗うときに、わざと水をばしゃっとかけて「ばぁー!」と遊びながら見せるようにしました。
すると子どもも真似して水を顔にかけて笑うようになり、自然に抵抗感が減っていきました。
体験談③ 泡遊びを取り入れる
石けんの泡に興味を持っていたので、「あわあわ〜」と言いながら一緒に泡を出して遊びました。
ポンプ式の石けんを使い、子どもの手に泡をのせて「ゴシゴシ」と声をかけると、自分の腕やお腹を洗う真似をするように。
こうした遊びを取り入れると「洗う=楽しい時間」に変わっていきます。
体験談④ お風呂を“遊び場”に変える
じっとしていられない日は、浴槽に数cmだけお湯をためて自由に遊ばせました。
その間にサッと身体を洗ってしまえば、お互いにストレスが減ります。
シャンプーやボトルを引っ張り出して遊ぶこともありましたが、危なくないものはできるだけ自由に触らせるようにしました。
「ダメ!」を連発するとお風呂自体が嫌になってしまうので、見守りつつ遊ばせるスタイルにしたのが良かったと思います。
体験談⑤ 無理をしない日もOK
眠くてぐずってどうしようもない日は、身体をざっと洗って終わりにする日もありました。
「毎日きっちり完璧に」よりも、「お風呂は嫌な場所じゃない」という感覚を優先した方が、結果的に長い目で見てプラスになりました。
6ヶ月健診際に保健師さんにも、「赤ちゃんが嫌がっている時に、無理やりお風呂に入れなくてもいい。」と言われていたのも心の安定につながりました。
「年齢別:お風呂嫌いへの向き合い方」
- 0〜1歳:シャワーを遊びに変える
- 1〜2歳:泡遊びやおもちゃを活用して「楽しい場所」に
- 3歳〜:自分で洗う・数を数えるなど「自立心・遊び学習」に
「お風呂習慣が育む“生活力”」
- 自分で体を洗う → 自己管理力
- 汚れを落とす → 清潔感や健康意識
- 寝る前のルーティン → 生活リズムの安定
- 遊びながら学ぶ → 好奇心や感覚統合
お風呂嫌い克服で得られる教育的メリット
お風呂は単なる衛生習慣ではなく、実は知育や発達にもつながる時間です。
- 感覚統合の発達
水の感触や温度変化を経験することで、五感が刺激され、感覚統合の力が育ちます。 - 模倣・学習能力の向上
親の動作を真似して「顔を洗う」「身体をゴシゴシする」などを覚えることで、日常生活のスキルが身につきます。 - 言葉の発達
「あわあわ」「ジャー」「ゴシゴシ」など擬音語を使うことで、楽しく言葉を覚えやすくなります。 - 安心できる親子のコミュニケーション
スキンシップや遊びを通じて「お風呂=楽しい時間」と認識することは、親子関係の安心感にもつながります。
厚生労働省も、幼児期には遊びや生活の中で五感を刺激する経験が大切だと解説しています。
お風呂はその実践の場としてぴったりなんです。
まとめ
わが家では「慣れる」「真似する」「遊ぶ」「自由にさせる」「無理をしない」の5つを意識することで、少しずつお風呂嫌いを克服できました。
子どもにとってお風呂は「訓練」ではなく「楽しい体験」であることが大切。
毎日の習慣の中で工夫を重ねることで、お風呂好きに変わるきっかけをつくれるはずです。