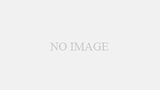はじめに:1歳1ヶ月、「自分で食べたい」が始まった日
1歳1ヶ月のある日の夕食。
子どもがスプーンを手に取り、こちらを見てにっこり。
それまでは食べさせてもらうのが当たり前だったけれど、
その日は明らかに違いました。
「今日は自分で食べたい!」
という意志が、目の奥にしっかりと感じられたんです!
こぼしても構わない。そう思って見守ると、
40分かけて、ゆっくり、ゆっくりと自分の手で食べきりました。
その姿を見ながら、
生後10ヶ月から始めたスプーン練習が単なる「食事」ではなく、
発達そのものだと実感した日でもありました。
スプーン練習がもたらす3つの発達効果
スプーン練習は、実は“遊び”や“訓練”の要素を多く含んでいます。
手先のコントロール、集中力、そして自己肯定感。
どれも日々の発達に欠かせない基礎です。
① 手指の巧緻性と脳の発達を促す
スプーンを使う動きは、一見単純なようでいて
脳内では非常に複雑なプロセスが行われています。
スプーンを握る力加減 、すくう角度の調整 、食材の重さや形状の感覚処理…
これらを何度も試行錯誤するうちに、
脳の運動野・小脳・前頭葉がフル稼働し、
「思考と運動をつなぐ力」 が育っていきます。
言葉がまだ少ない時期でも、
手の動きが脳を刺激し、発達を加速させるのです。
② 集中力と持続力を育てる
自分で食べるという行為は、
「目的行動」の連続そのもの。
食べたい → すくう → 運ぶ → こぼす → 修正する
この繰り返しが集中力の土台を作ります。
大人から見ると“ゆっくりすぎる40分”でも、
子どもにとっては「やりきる力」を試している時間。
この積み重ねが、のちの「集中できる子」につながっていきます。
③ 自己肯定感と達成感を高める
親がすぐに手を出さずに見守ることで、
「できた!」という感情を自分の中で味わうことができます。
完璧じゃなくてもいい。
こぼしても、汚れても、自分で食べきった事実が自信の芽になります。
「今日も自分で食べられた」
「パパが笑ってくれた」
その積み重ねこそが、自己肯定感の基礎です。
パパができる関わり方3選
1歳前後のスプーン練習では、「どう教えるか」よりも
「どう見守るか」が大切です。
① 成功より「挑戦」をほめる
「うまくできたね」よりも、
「がんばってるね」
「自分でやろうとしてるね」
という声かけが、子どもの意欲を引き出します。
② 予告とリズムをつける
いきなり始めると集中が途切れがち。
「もうすぐごはんだよ」
「スプーンでトントンしてから食べようか」
など、リズムと言葉の予告を入れるとスムーズです。
③ 一緒に食卓を囲む
「パパと一緒に食べる時間」をつくるのもおすすめ。
同じ空間で食べることで、
「食事=楽しい時間」という印象が自然に育ちます。
実体験:40分の挑戦を見守って
あの日の夕食は、正直言って長かった。
途中で「手伝ってしまおうか」と何度も思いました。
でも、「今日は本人がやりたい日だ」と思い直して、
手を出さずに見守り続けました。
食べ終わるころには、テーブルも服もすごいことになっていましたが、
本人の顔には達成感がいっぱい。
スプーンを置いて遊びに席を立った瞬間、
自然と拍手していました。
成功よりも、「自分でやりきった経験」。
それが、子どもの次の挑戦を支える。
今後について
ひとりで食べきった次の日。
一切、自分では食べませんでした(笑)
そして量も、全然食べない。
自分で食べることができたからといって、もう完璧!とはならないのが子育て。
だから、「昨日はできたのに…」とは思わず、
「今日は気が乗らないのかな」と考えて、前向きにやっていこうと思います。
まとめ:スプーン練習は「発達と信頼」を育てる時間
スプーン練習を通して学べるのは、
ただの「食べる技術」ではありません。
手と脳を連動させる力 集中して取り組む力 自分を信じる力
そして何より、
**「パパが見守ってくれている安心感」**が子どもの心を育てます。
食事の時間は、発達の時間であり、信頼の時間。
今日の「40分」は、子どもが自分を信じる力を育てた40分でした。
あわせて読みたい記事
1歳児 スプーン練習の関連記事
スプーン練習はいつから始める?
そんな悩みをお持ちの方はコチラ↓
スプーン練習ってなにから始めたらいいの?
そんな悩みをお持ちの方はコチラ↓
まずは、手づかみ食べから!
散らかすだけで、食べてくれなーい!
そんな悩みをお持ちの方はコチラ↓
パパ目線で解説!手づかみ食べいつから?始め方と発達メリット徹底ガイド
1歳児発達支援の関連記事
遊ぶの大好き!
子どもと遊ぶアイディアが欲しい方はコチラ↓
1歳児あるある!
楽しくなったり、嫌なことがあるとおもちゃを投げる…。
我が家の解決法はコチラ↓
1歳がおもちゃを投げる理由と対処法|我が家で効果があった対策
親の声かけで言葉の発達を促す。
毎日のちょっとした工夫が大切↓